どうも、哀歌です。
今回は、昨年度の事例Ⅲの問題の取り組み方について、実際に昨年の試験で行った方法を紹介したいと思います。
昨年度の事例Ⅲの得点は69点と最も高かったので、一つの事例として参考になるかと思います。
ちなみに、自分は製造業の現場について詳しい知識を持っているわけではありません。
むしろ現場を知っている人の方が、採点者が要求していない方向の回答を行うことがあるので、製造現場を知らないといって不利になることは全くありません!
それでは、順を追って説明いたしましょう。
C社はトラブル続きのダメダメ企業
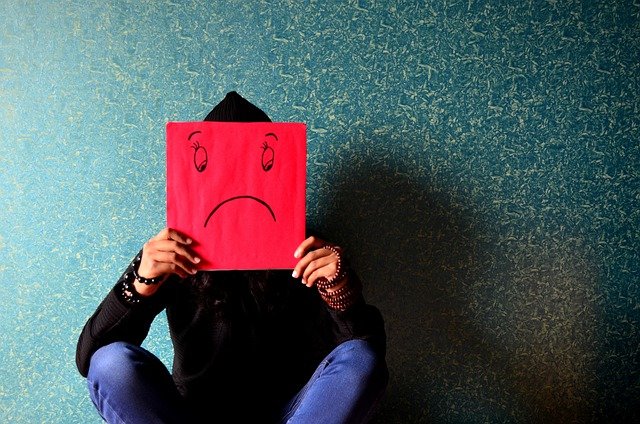
基本的に常に何かしらのトラブルが発生しているのがC社です。
トラブルが起きていなければ改善の助言をすることができないので当たり前ですが、そうは言っても毎年のように現状に困っているC社が取り上げられていますね。
与件文を見ると、発生している問題に関する記述が多いです。
つまり、事例Ⅲの問題は端的に言うと、現状のC社で起きているトラブルや、今後困ったことになりそうな状況を推測し、改善方法を的確に指摘することが求められているといえますね。
というわけで、現状のC社は一体何に困っているのか。それを丁寧に与件文から抽出していく必要があります。
与件文からC社が抱えるトラブルや問題点を拾い上げていく
事例Ⅲは、発生しているトラブルが与件文に分かりやすく書かれています。
ここでは令和2年度の事例Ⅲの与件文を参考に、問題点をいくつか抽出してみましょう。
・図面承認後の製作段階でも打ち合わせが必要な場合がある。
・製作期間が生産計画をオーバーするなど、納期の遅延が生じC社の大きな悩みとなっている。
・各作業チームの技術力には差があり、高度な技術が必要な制作物の場合には任せられない作業チームもある。
・この際、デザイナーの指示によって製品に修整や手直しが生じる場合がある。
・C社の製品については基準となる工程順序や工数見積もりなどの標準化が確立しているとはいえない。
・最近の加工物の大型化によって狭隘な状態が進み、溶接・組立工程と研磨工程の作業スペースの確保が難しく……
・不稼働の作業内容としては、「材料・工具運搬」と~
ということが書かれていますね。
そういった問題の解決策であったり、C社自身が認識していない課題や問題を「ここが良くないですよー」と指摘してあげることが事例Ⅲの問題です。
なので、私は与件文を読みながらC社が抱えているトラブルに下線を引きながら問題点を明らかにしていました。
トラブルに対してシンプルな解決法をメモしていく
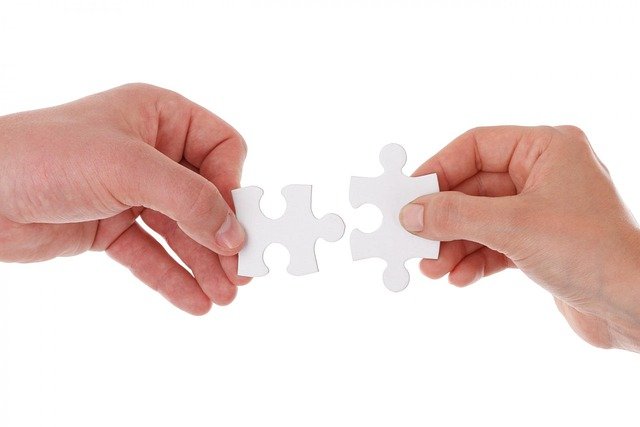
勿論、対応策や解決策を助言する問題では、その方法を考えなければならないですが、助言を難しく考えすぎると泥沼にはまっていきます(私は)
「もっと中小企業診断士らしく、的確な助言をしなくては!」
「今は本番の試験なんだ! こんな回答では点数がもらえないのでは!?」
というプレッシャーも感じて、考えすぎてしまう傾向にありました。
なので、私が採用した方法というのが、
「まず超シンプルな助言をしてみること」
でした。
それでは、先程挙げた問題や課題を例にやってみましょう。
・図面承認後の製作段階でも打ち合わせが必要な場合がある。
→じゃあ打ち合わせが必要にならないようにすればいいんじゃね?
・製作期間が生産計画をオーバーするなど、納期の遅延が生じC社の大きな悩みとなっている。
→生産計画をオーバーせず、納期の遅延が発生しないようにすればいいんじゃね?
・各作業チームの技術力には差があり、高度な技術が必要な制作物の場合には任せられない作業チームもある。
→技術力に差がないようにすればいいんじゃね?
・この際、デザイナーの指示によって製品に修整や手直しが生じる場合がある。
→修整や手直しが生じないようにすればいいんじゃね?
・C社の製品については基準となる工程順序や工数見積もりなどの標準化が確立しているとはいえない。
→工程順序や工数見積もりなどを標準化すればいいんじゃね?
・最近の加工物の大型化によって狭隘な状態が進み、溶接・組立工程と研磨工程の作業スペースの確保が難しく……
→作業スペースを確保すればいいんじゃね?
・不稼働の作業内容としては、「材料・工具運搬」と~
→不稼働の作業内容を発生すればいいんじゃね?
と、こんな感じです。
勿論、こうすりゃいいんじゃね? という形でそのまま回答してはいけませんよ(笑)
理想の形に近付けられるように段階を追って方法を考える

そんなこと誰だってできるわ! と思う方もいらっしゃるでしょう。
ですが、この超シンプルな助言が、C社が目指す理想の姿なのではないでしょうか。
勿論、私が書いたこの助言をそのまま回答にするわけにもいかないので、一つずつ段階を踏んで回答にしていけばいいのではないでしょうか。
例えば、
・各作業チームの技術力には差があり、高度な技術が必要な制作物の場合には任せられない作業チームもある。
という点に関しては、
『技術力に差がないようにすればいいんじゃね?』→『そのためには他の作業者も育成すればいいんじゃね?』→『作業の方法を分かりやすくして育成しやすいんじゃね?』
こんな感じですね。
なので、与件文で問題点を抽出して後、その傍に理想の形をメモしていきました。
実際の試験なので、当然緊張します。
こんな回答でいいのだろうか、と迷うことも多々あるでしょう。
ですが、まずは一旦シンプルに考えて、
『こういう状態になれば問題が解決するのになー』
と、簡単に考えてみるのも重要なのではないでしょうか。
終わりに
あくまで昨年度の自分の取り組み方ですが、この考え方で69点まで積み上げてきたので間違ってはいないかと思います。
繰り返しますが、C社はトラブルだらけの困った会社です。
なので、まずはシンプルに「できていないことをできるようにしましょう」と考えてみてはいかがでしょうか。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。








コメント